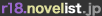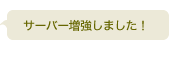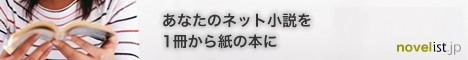平和な復讐
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和4年11月時点のものです。
時代ごとの問題
今年、35歳になった刑部雅人は、会社では主任となり、今までの第一銭で先陣を切ってきた仕事もこなしながら、部下を意識しなければならない年齢になってきた。
同僚からの信頼も厚かったので、主任になっても、今までと変わらずに仕事ができるだろうと思っていたのだったが、実際に部下というものを持ってみると、思ったよりも、大変そうだということが分かってきた。
あまり、気にしなければいいだけのことなのだろうが、刑部は神経質なところがあった。それもいい意味での神経質も、悪い意味での神経質も、両方が混在しているので、自分でも混乱してしまうことが多かった。
そういう意味で、昨年、会社の近くに引っ越してきたのだが、前、住んでいたところから会社までは、結構な時間が掛かり、電車の乗り換えも頻繁だったこともあって、正直通勤だけで疲れていた。
残業などをすると、帰宅するのが、夜の10時以降などということも頻繁で、腹が減ると、どうしても、先に食事をしてから帰ろうと思うと、終電手前になることも少なくなったのだった。
20歳代の頃まではそれでも、別によかったのだが、30代になると、どうにも落ち着かなくなってきた。最初は、
「何が違うのだろう?」
と思っていたが、最近は、その理由が分かってきたのだ。
「ああ、終電に近くなればなるほど、電車が混んでくるんだ」
ということに気づいたからだ。
20代の頃までは、それほど、電車の混み具合を気にすることはなかった。
「座ってはいけるんだから、問題はない」
と思っていたのだ。
だが、30代にあると、どうにも電車の中のせわしなさに気づいてしまうと、苛立ちを抑えられなくなるのだった。
気が付くと、電車の中のマナーの悪さが目に付くようになった。
本来なら、別にマナーが悪いわけではないことまで、煩わしく感じられるようになると、自分の中での、
「マナーというルールに引っかかるんだよな」
と思うようになっていたのだ。
マナーが悪いからといって、別に犯罪ではない。警察につかまったり、処罰されたり、罰金を取られるわけではない。だから、それだけに、マナーの悪い連中は、それが分かっているから、あざとく感じられ、いかにも、
「確信犯」
に思えてくるのだった。
そう思うと、それまで、気にもしなかったことが気になってくる。特に、電車の中で多く散見され、次第に、街を歩いていても、
「どいつもこいつも」
という印象になってくるのだった。
特に、道を歩いている時のマナー違反は、目に余るものがある。
確かに、マナー違反くらいであれば、別に、
「人に迷惑をかけている」
というだけで、犯罪として扱われない。
むしろ、
「まわりが我慢しなければいけない」
などという、とんでもない理屈となったりしているのだった。
特に歩道などというところは、法律的には実に曖昧なところだ。
実際には、確固たる法律はあるのだが、ほとんど認識されていないといってもいい。被害に遭っている方だって、それがただの迷惑行為でしかないと思っているのだから、そもそもの教育がなっていないということになるのだろう。
それが、
「歩道による自転車走行」
という問題だった。
自転車と車の関係は法律でも明確になっていて、認識もかなりのものがあるだろう。
というのも、自転車よりも、何かあった時に一番立場が弱いのは、自動車だからである。もちろん、
「立場が自転車よりも弱い」
という意味では、バイクも同じことだが、ここでは、自動車として、一括りにしてもいいだろう。
道路交通法も、毎年のように改正されていたりして、正直、自転車の走行も、昭和の頃に比べて、かなり変わってきたことだろう。
何といっても、昔は、ヘルメット着用義務もなければ、横断歩道の右折も、車のようにできた。今のように、信号に正対しての走行でなければいけないということはなかったのだ。
ただ、これは、自転車に限ったことではない。車においてのシートベルト着用、さらには、小型特殊の運転の厳しさなどである。
昔は、曖昧だったこともあって、倉庫内であれば、フォークリフトも、運転免許証がなくても、誰でも乗れた。今はヘルメット着用も義務だし、教習も受けなければいけない時代になってしまった。
「世知辛い世の中だな」
ともいえるだろう。
しかし、実際に、道路交通法は、明文化されていることを、実際に誰も知らなかったり、勘違いをしていることが結構多かったりする。
それは、特に自転車において多いのではないだろうか?
「自転車は、どこを走行すべきなのか?」
と聞かれて、
「歩道を走行」
と答える人も少なくはないだろう。
何しろ、自転車に乗るのに、運転免許証がいるわけではなく、講習を受ける義務もない。学校などで、講習を行うところもあるだろうが、小学生であれば、どこまで理解できるというのか、
「自転車は、歩道を走るもの」
と真剣に思い込んでいる人はかなりいるのではないだろうか?
正確には、
「自転車は、車道を走らなけれはならない。車道の一番左側を走行し、車の走行を妨げてはいけない」
ということになるのだろう。
だから、車道を走ることは許されない。
許される場合もあるにはあるが、次の四つの場合しか、できないことである。
「自転車走行可」
「13歳未満の児童や、70歳以上の高齢者」
「身体障害者」
「客観的に見て、車道を走行することが困難な場合」
という時に限られる。
最後の、
「客観的に見て」
というのは、あくまでも、自分勝手な判断ではなく、誰が見ても、困難な場合に限られるということである。
前述のような、走行してもいい場合でも、歩道は、
「絶対的に歩行者優先」
本来であれば、運転してはいけないところを、
「運転させてもらっているのだから、当然、肩身が狭いのは当たり前。しかし、実際には、我が者顔で運転しているのだから、たちが悪い」
といってもいいだろう。
それだけ、歩行者と自転車の間では、走行についての温度差があるということだ。
特に最近は、
「食事の宅配という感じで、まるで、
「ここは俺の道」
と言わんばかりの我が物顔走行をしていると、本当に事故だって起こっていることだろう。
数年前に、ワイドショーなどで取り上げられはしたが、しょせん、その時だけのことで、放送局側も、
時代ごとの問題
今年、35歳になった刑部雅人は、会社では主任となり、今までの第一銭で先陣を切ってきた仕事もこなしながら、部下を意識しなければならない年齢になってきた。
同僚からの信頼も厚かったので、主任になっても、今までと変わらずに仕事ができるだろうと思っていたのだったが、実際に部下というものを持ってみると、思ったよりも、大変そうだということが分かってきた。
あまり、気にしなければいいだけのことなのだろうが、刑部は神経質なところがあった。それもいい意味での神経質も、悪い意味での神経質も、両方が混在しているので、自分でも混乱してしまうことが多かった。
そういう意味で、昨年、会社の近くに引っ越してきたのだが、前、住んでいたところから会社までは、結構な時間が掛かり、電車の乗り換えも頻繁だったこともあって、正直通勤だけで疲れていた。
残業などをすると、帰宅するのが、夜の10時以降などということも頻繁で、腹が減ると、どうしても、先に食事をしてから帰ろうと思うと、終電手前になることも少なくなったのだった。
20歳代の頃まではそれでも、別によかったのだが、30代になると、どうにも落ち着かなくなってきた。最初は、
「何が違うのだろう?」
と思っていたが、最近は、その理由が分かってきたのだ。
「ああ、終電に近くなればなるほど、電車が混んでくるんだ」
ということに気づいたからだ。
20代の頃までは、それほど、電車の混み具合を気にすることはなかった。
「座ってはいけるんだから、問題はない」
と思っていたのだ。
だが、30代にあると、どうにも電車の中のせわしなさに気づいてしまうと、苛立ちを抑えられなくなるのだった。
気が付くと、電車の中のマナーの悪さが目に付くようになった。
本来なら、別にマナーが悪いわけではないことまで、煩わしく感じられるようになると、自分の中での、
「マナーというルールに引っかかるんだよな」
と思うようになっていたのだ。
マナーが悪いからといって、別に犯罪ではない。警察につかまったり、処罰されたり、罰金を取られるわけではない。だから、それだけに、マナーの悪い連中は、それが分かっているから、あざとく感じられ、いかにも、
「確信犯」
に思えてくるのだった。
そう思うと、それまで、気にもしなかったことが気になってくる。特に、電車の中で多く散見され、次第に、街を歩いていても、
「どいつもこいつも」
という印象になってくるのだった。
特に、道を歩いている時のマナー違反は、目に余るものがある。
確かに、マナー違反くらいであれば、別に、
「人に迷惑をかけている」
というだけで、犯罪として扱われない。
むしろ、
「まわりが我慢しなければいけない」
などという、とんでもない理屈となったりしているのだった。
特に歩道などというところは、法律的には実に曖昧なところだ。
実際には、確固たる法律はあるのだが、ほとんど認識されていないといってもいい。被害に遭っている方だって、それがただの迷惑行為でしかないと思っているのだから、そもそもの教育がなっていないということになるのだろう。
それが、
「歩道による自転車走行」
という問題だった。
自転車と車の関係は法律でも明確になっていて、認識もかなりのものがあるだろう。
というのも、自転車よりも、何かあった時に一番立場が弱いのは、自動車だからである。もちろん、
「立場が自転車よりも弱い」
という意味では、バイクも同じことだが、ここでは、自動車として、一括りにしてもいいだろう。
道路交通法も、毎年のように改正されていたりして、正直、自転車の走行も、昭和の頃に比べて、かなり変わってきたことだろう。
何といっても、昔は、ヘルメット着用義務もなければ、横断歩道の右折も、車のようにできた。今のように、信号に正対しての走行でなければいけないということはなかったのだ。
ただ、これは、自転車に限ったことではない。車においてのシートベルト着用、さらには、小型特殊の運転の厳しさなどである。
昔は、曖昧だったこともあって、倉庫内であれば、フォークリフトも、運転免許証がなくても、誰でも乗れた。今はヘルメット着用も義務だし、教習も受けなければいけない時代になってしまった。
「世知辛い世の中だな」
ともいえるだろう。
しかし、実際に、道路交通法は、明文化されていることを、実際に誰も知らなかったり、勘違いをしていることが結構多かったりする。
それは、特に自転車において多いのではないだろうか?
「自転車は、どこを走行すべきなのか?」
と聞かれて、
「歩道を走行」
と答える人も少なくはないだろう。
何しろ、自転車に乗るのに、運転免許証がいるわけではなく、講習を受ける義務もない。学校などで、講習を行うところもあるだろうが、小学生であれば、どこまで理解できるというのか、
「自転車は、歩道を走るもの」
と真剣に思い込んでいる人はかなりいるのではないだろうか?
正確には、
「自転車は、車道を走らなけれはならない。車道の一番左側を走行し、車の走行を妨げてはいけない」
ということになるのだろう。
だから、車道を走ることは許されない。
許される場合もあるにはあるが、次の四つの場合しか、できないことである。
「自転車走行可」
「13歳未満の児童や、70歳以上の高齢者」
「身体障害者」
「客観的に見て、車道を走行することが困難な場合」
という時に限られる。
最後の、
「客観的に見て」
というのは、あくまでも、自分勝手な判断ではなく、誰が見ても、困難な場合に限られるということである。
前述のような、走行してもいい場合でも、歩道は、
「絶対的に歩行者優先」
本来であれば、運転してはいけないところを、
「運転させてもらっているのだから、当然、肩身が狭いのは当たり前。しかし、実際には、我が者顔で運転しているのだから、たちが悪い」
といってもいいだろう。
それだけ、歩行者と自転車の間では、走行についての温度差があるということだ。
特に最近は、
「食事の宅配という感じで、まるで、
「ここは俺の道」
と言わんばかりの我が物顔走行をしていると、本当に事故だって起こっていることだろう。
数年前に、ワイドショーなどで取り上げられはしたが、しょせん、その時だけのことで、放送局側も、