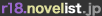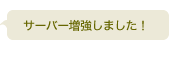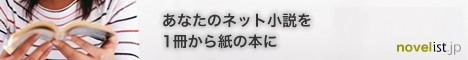痛み分けの犯罪
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和5年2月時点のものです。いつものことですが、似たような事件があっても、それはあくまでも、フィクションでしかありません、ただ、フィクションに対しての意見は、国民の総意に近いと思っています。ただ、今回のお話はフィクションではありますが、作者の個人的な苛立ちが大いに入っていることをご了承ください。今回の小説は、日本の未来について、少し作者が憂いたところから始まっております。
エントランス
ある会社が入っている雑居ビルである。
都心部に近いところにあり、その場所というのは、駅前から斜めに走っている片側2車線という大通りに面したところにあった。
それでも、駅からは20分近く徒歩でかかるので、そこまで遠くはないとはいえ、通勤圏内としては、ギリギリというところであろうか。
ただ、駅前から途中までは地下道が通っていて、ある意味、便利がいい。そこまでは、信号を使う必要がないからだった。
さらに、地下道の下を、地下鉄が通っていて、地下道は、その地下鉄の、ちょうと一駅分ということで、かなり楽ができるのだった。
地下道自体は、地下鉄よりも、少し後にできていて、元々、この駅の周辺には、コンピュータ関係の会社が乱立していたのだが、地下道ができてから、5年もしないうちに、郊外の埋め立て地に、以前、博覧会を行ったことのある跡地に移転することで、実際には、地下道を通る人が、相当減ったのだった。
だが、さすがに一度掘った地下道を、再度埋めるなどというバカげたことをするはずもなく、今でも利用している。
特に、地下道の半分は、自転車駐輪場になっていて、これは、コンピュータ会社が乱立し、賑やかだった頃から変わっていない。
「時代を読み間違えた」
と言えるかも知れないが、いまだに使用している人は少なくない。
何と言っても、コンピュータ会社が抜けた後に、新しくビルを建て替えて、違う会社も入ってきているのも、事実だ。
しかし、バブルが弾けてからこっちは、都心部の家賃の高いところにわざわざ事務所を借りる会社も減ってきていて、
「埋まっても、半分くらいがいいところか?」
ということになった。
というのも、立て方としては、こじんまりとした事務所を想定していることで、部屋がいっぱいできてしまった。一つの部署で一つの事務所というくらいのところが多いので、
「事務所が埋まらない」
というのも、無理もないということなのだろう。
それを思うと、
「都心部は、どんどん事務所が減っていって、ドーナツ化現象になるんだろうか?」
と考える。
というのも、バブルが弾けてからこっち、
「経費節減」
ということで、
「家賃の高い都心部に事務所を借りるなどもったいない」
ということと、さらに、
「郊外に、物流センターを建設する」
という計画を持っている企業は、そこに本部機能を移管する方法を取っているところがあるのだった。
これは、経費以前の問題で、インフラの関係から、
「高速道路の近くに物流センターが多い」
ということを考えても分かるように、それだけ、交通の便の良さが、そのまま流通による、
「時間の無駄」
を省くことができるということが、一番の理由だった。
そうでもないと、
「あんな不便な会社と取引するよりも、高速の近くの便利のいい企業と取引をする方が、便利でいい」
ということで、便宜上を優先する会社だってたくさんあるからだった。
郊外型の流通センターは、一時期流行った。
今もたくさんあるわけだが、それは、昔からと比べて、流通の在り方というか、
「流通業の考え方が変わってきた」
ということが大きいのかも知れない。
特に、昭和の頃のスーパー関係などの展開が変わってきたからだ。
詳しいことは分からないが、時期的に、
「コンビニがどんどん、全国で増え始めた」
というところから始まってるのかも知れない。
コンビニエンスストアというと、正直、
「読んで字のごとく」の、
「便利さ」
というものなのだろうが、便利さとはあくまでも、
「24時間開いている」
というだけで、それ以外は、
「品ぞろえは悪いし、あっても、数個しか置いていないので、すぐに売り切れる」
というものだ。
しかも、フランチャイズの関係なのか知らんが、
「同じ名前のコンビニでも、徒歩5分くらいの近くにある店であっても、品ぞろえがまったく違うのだ」
つまりは、
「同じチェーンでも、置いてあるところと置いてないところがある」
ということで、
「チェーン店で、ほしいものがあるか、あるいはないのか?」
ということがまったく分からない。
「これで何がコンビニなのか?」
と思う人は、結構いるのではないかとか思うのだ。
「時間以外は、行く気もしない」
と言いたい。
特に、レジ袋が有料になった時などひどかった。
というのも、
「レジ袋の有料化」
ということで、確かにそれまでは、サービスだったので、袋の大きさを、相手が決めるのは、
「百歩譲って」
許されることかも知れないが、スーパーであれば、
「客の申す通り」
もくれていたものだった。
しかし、今度は逆に、レジ袋が商品になったのだ。
普通であれば、
「一番大きなものをください」
といえば、コンビニであろうが、どこであろうが、対価を支払うものに対して、
「こちらにしてください」
とは言えないはずだ。
コンビニの場合、それを明記してあるところがあった。
「レジ袋は、買い物の量に合わせてください」
なる文句を見たことがあった。
これが、無料のサービスであれば、客も文句は言えないのかも知れないが、それも、おかしな話だ。商品を買ってもらった相手に、それをいうのは違うと思う。
それはさておき、お金を取っておきながら、このいい分は、通らないだろう。
レジ袋だって、お金を取る以上、
「通常商品」
と変わらない。
つまり、同じ商品であるが、
「5円のものではなく、3円のものにしてください」
と言っているようなものだ。
「5円のものをください」
といって、
「いいえ、3円のものしか売れません」
などというのはありであろうか?
お米を買いに行って、
「10kgください」
といっても、
「2kgにしてください」
で許されるのか?
エントランス
ある会社が入っている雑居ビルである。
都心部に近いところにあり、その場所というのは、駅前から斜めに走っている片側2車線という大通りに面したところにあった。
それでも、駅からは20分近く徒歩でかかるので、そこまで遠くはないとはいえ、通勤圏内としては、ギリギリというところであろうか。
ただ、駅前から途中までは地下道が通っていて、ある意味、便利がいい。そこまでは、信号を使う必要がないからだった。
さらに、地下道の下を、地下鉄が通っていて、地下道は、その地下鉄の、ちょうと一駅分ということで、かなり楽ができるのだった。
地下道自体は、地下鉄よりも、少し後にできていて、元々、この駅の周辺には、コンピュータ関係の会社が乱立していたのだが、地下道ができてから、5年もしないうちに、郊外の埋め立て地に、以前、博覧会を行ったことのある跡地に移転することで、実際には、地下道を通る人が、相当減ったのだった。
だが、さすがに一度掘った地下道を、再度埋めるなどというバカげたことをするはずもなく、今でも利用している。
特に、地下道の半分は、自転車駐輪場になっていて、これは、コンピュータ会社が乱立し、賑やかだった頃から変わっていない。
「時代を読み間違えた」
と言えるかも知れないが、いまだに使用している人は少なくない。
何と言っても、コンピュータ会社が抜けた後に、新しくビルを建て替えて、違う会社も入ってきているのも、事実だ。
しかし、バブルが弾けてからこっちは、都心部の家賃の高いところにわざわざ事務所を借りる会社も減ってきていて、
「埋まっても、半分くらいがいいところか?」
ということになった。
というのも、立て方としては、こじんまりとした事務所を想定していることで、部屋がいっぱいできてしまった。一つの部署で一つの事務所というくらいのところが多いので、
「事務所が埋まらない」
というのも、無理もないということなのだろう。
それを思うと、
「都心部は、どんどん事務所が減っていって、ドーナツ化現象になるんだろうか?」
と考える。
というのも、バブルが弾けてからこっち、
「経費節減」
ということで、
「家賃の高い都心部に事務所を借りるなどもったいない」
ということと、さらに、
「郊外に、物流センターを建設する」
という計画を持っている企業は、そこに本部機能を移管する方法を取っているところがあるのだった。
これは、経費以前の問題で、インフラの関係から、
「高速道路の近くに物流センターが多い」
ということを考えても分かるように、それだけ、交通の便の良さが、そのまま流通による、
「時間の無駄」
を省くことができるということが、一番の理由だった。
そうでもないと、
「あんな不便な会社と取引するよりも、高速の近くの便利のいい企業と取引をする方が、便利でいい」
ということで、便宜上を優先する会社だってたくさんあるからだった。
郊外型の流通センターは、一時期流行った。
今もたくさんあるわけだが、それは、昔からと比べて、流通の在り方というか、
「流通業の考え方が変わってきた」
ということが大きいのかも知れない。
特に、昭和の頃のスーパー関係などの展開が変わってきたからだ。
詳しいことは分からないが、時期的に、
「コンビニがどんどん、全国で増え始めた」
というところから始まってるのかも知れない。
コンビニエンスストアというと、正直、
「読んで字のごとく」の、
「便利さ」
というものなのだろうが、便利さとはあくまでも、
「24時間開いている」
というだけで、それ以外は、
「品ぞろえは悪いし、あっても、数個しか置いていないので、すぐに売り切れる」
というものだ。
しかも、フランチャイズの関係なのか知らんが、
「同じ名前のコンビニでも、徒歩5分くらいの近くにある店であっても、品ぞろえがまったく違うのだ」
つまりは、
「同じチェーンでも、置いてあるところと置いてないところがある」
ということで、
「チェーン店で、ほしいものがあるか、あるいはないのか?」
ということがまったく分からない。
「これで何がコンビニなのか?」
と思う人は、結構いるのではないかとか思うのだ。
「時間以外は、行く気もしない」
と言いたい。
特に、レジ袋が有料になった時などひどかった。
というのも、
「レジ袋の有料化」
ということで、確かにそれまでは、サービスだったので、袋の大きさを、相手が決めるのは、
「百歩譲って」
許されることかも知れないが、スーパーであれば、
「客の申す通り」
もくれていたものだった。
しかし、今度は逆に、レジ袋が商品になったのだ。
普通であれば、
「一番大きなものをください」
といえば、コンビニであろうが、どこであろうが、対価を支払うものに対して、
「こちらにしてください」
とは言えないはずだ。
コンビニの場合、それを明記してあるところがあった。
「レジ袋は、買い物の量に合わせてください」
なる文句を見たことがあった。
これが、無料のサービスであれば、客も文句は言えないのかも知れないが、それも、おかしな話だ。商品を買ってもらった相手に、それをいうのは違うと思う。
それはさておき、お金を取っておきながら、このいい分は、通らないだろう。
レジ袋だって、お金を取る以上、
「通常商品」
と変わらない。
つまり、同じ商品であるが、
「5円のものではなく、3円のものにしてください」
と言っているようなものだ。
「5円のものをください」
といって、
「いいえ、3円のものしか売れません」
などというのはありであろうか?
お米を買いに行って、
「10kgください」
といっても、
「2kgにしてください」
で許されるのか?