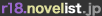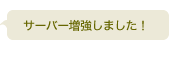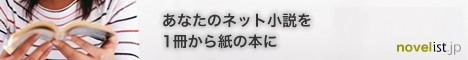矛盾による循環
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和5年2月時点のものです。いつものことですが、似たような事件があっても、それはあくまでも、フィクションでしかありません、ただ、フィクションに対しての意見は、国民の総意に近いと思っています。ただ、今回のお話はフィクションではありますが、作者の個人的な苛立ちが大いに入っていることをご了承ください。今回の精神医療の話は、実際に調査したものではなく、小説の中でのストーリー展開として、都合よく描いているところがあるので、信じないようにお願いします。また、行われている研究も、実に都合よく書いているだけなので、そのあたりも、御当社頂ければ幸いです。
長所と単所
「長所は短所は紙一重」
という言葉はよく耳にすることがある。
意味としては、分かるし、耳に慣れているということから、別に違和感を感じることはないといえるだろう。
しかし、冷静に考えてみると、
「どこかがおかしい」
と感じないだろうか?
長所というのは、自分にとって、いいことであり、武器にもなることなのだ。しかし、実際に、そうなのだろうか?
確かに、長所というのは、自分にとって、いいことだというのであれば、それは、ある意味他人にとって、
「そこまでのことはない」
と言えることではないだろうか?
むしろ、その人にいいことであるものは、ライバルにとっては、
「そんなものがあると、自分が上にいけないじゃないか?」
と思うことだろう。
それは嫉妬に繋がってみたり、自分の中で勝手に焦りとなってしまうことだってあることだろう。
だが、それは、相手と、
「まだまだ仲良くなっていない」
ということを示している。
仲良くならないまでも、ライバルとして、お互いにリスペクトをするのであれば、相手の立場を分かってあげたり、心境を分かってあげたりしないと、相手に、
「こちらのことも分かれ」
というのは、勝手な都合でしかないだろう。
そんなことを考えていると、
人と仲良くなるということは、まずは、相手に興味を持つことが大切だ。興味もない相手と、そもそも、仲良くなろうという発想などなく、もし、これが、
「相手を利用しよう」
という考えであれば、それは、
「仲良く」
ということではなく、
「あくまでも、自分の利益優先」
ということになってしまい、そこで、お互いの立場関係を明確にしたいという意思が生まれてくるのだろう。
いわゆる、
「マウントを取る」
という考えになるのであって、最初から、お互いの力関係を考えての人間関係に、
「仲良く」
というワードがついてくるわけはない。
もちろん、次第に、お互いに共通点を持っているとすれば、その共通点がお互いに励みとなり、
「一足す一が二」
ではなく。
「三にも四にもなる」
ということを追い求める関係になるというのは、いいことではないだろうか。
それがいわゆる、
「ライバル」
というものであり、逆に、
「ライバルがいないと、士気が上がらない」
ともいえるかも知れない。
軍隊などでもそうではないか。平時には、日ごろから訓練を行っているが、その時には、必ず、仮想敵なるものがあって、その存在を撃破するべく、訓練を行っているわけである。
もちろん、実際に敵が現れて、そこが、まったく仮想敵とは違ったものである可能性もなきにしもあらずであるが、だからといって、
「すべての国を仮想敵として訓練する」
というのは、まず不可能なことで、
「どこか一つ、有事になる可能性があるか、あるいは、訓練するのに、ふさわしい国を定めて仮想敵とする」
というのが、一番ふさわしいことなのではないだろうか?
あくまでも、戦争における、
「仮想敵」
という発想だから、どうしても、そうなってしまうのであって、スポーツや、趣味のライバルであれば、まずは、自分のレベル向上に向けての努力を惜しむことなく行い、そして、初めて、ライバルである相手を意識して、相手の情報を収集し、さらに、同時に自分の力量というものをわきまえたところで、初めて、自分のレベルが相手に対して、どのあたりにいるのかということを考えることで、
「仮想敵」
というものを、まともに意識することができるのだろう。
「相手が見えていないと、とても相手になるものではない」
ということで、ライバルが見えるようになることは、自分が成長する過程での、
「通過点」
であり、
「自分を顧みることができる」
いや、
「しなければいけない」
という場所なのだろう。
「ライバルというものは、こちらの長所も短所も分かっているのだろうか?」
と考えることがある。
例えば、野球などでもそうなのだが、
「得意なコースの近くに、弱点がある」
などと言われたりする。
それじゃあ、
「相手の弱点が分かっているのだから、こちらのものだ」
というと、
「おっとどっこい、そういうわけにはいかない」
つまりは、人間の心理的なものが問題になるのであろう。
ただ、その前に、根本的に考えることがあった。
というのは、
「ライバルが一人とは限らない」
というものだった。
というのは、昔の昭和時代に流行った、
「スポーツ根性もの」
などのことであるが、よくあるのが、
「魔球のようなものを開発して、ライバルと戦う」
というものであった。
身体を駆使したり、理論的に相手がそのボールを理解しなければ、
「まず打倒することはできない」
というものがあるだろう。
そんなマンガや、テレビアニメには、まず、パターンがある。
「ライバルが数人いることや、特訓してライバルに打てないような、もっといえば、ライバルに打てないのだから、他の選手に打てるわけはないという設定」
というものがある、
そして、
「こちらが血の滲むような特訓で、魔球を編み出すと、ライバルたちは、外の選手との勝負を二の次にして、ライバルとの勝負に勝つために、必死になる」
というのだ。
主人公が開発した魔球は、ほとんどの場合、
「普通の打法では打倒が不可能」
というような球を投げてくるのだ。
その魔球を攻略しようと考えると、自ずと、それまでの打ち方がおろそかになってしまい、いわゆる、
「基本の打法」
というものから外れてくることになる。
ということは、
「普通に投げてくう選手のボールが打てなくなる」
ということである。
長所と単所
「長所は短所は紙一重」
という言葉はよく耳にすることがある。
意味としては、分かるし、耳に慣れているということから、別に違和感を感じることはないといえるだろう。
しかし、冷静に考えてみると、
「どこかがおかしい」
と感じないだろうか?
長所というのは、自分にとって、いいことであり、武器にもなることなのだ。しかし、実際に、そうなのだろうか?
確かに、長所というのは、自分にとって、いいことだというのであれば、それは、ある意味他人にとって、
「そこまでのことはない」
と言えることではないだろうか?
むしろ、その人にいいことであるものは、ライバルにとっては、
「そんなものがあると、自分が上にいけないじゃないか?」
と思うことだろう。
それは嫉妬に繋がってみたり、自分の中で勝手に焦りとなってしまうことだってあることだろう。
だが、それは、相手と、
「まだまだ仲良くなっていない」
ということを示している。
仲良くならないまでも、ライバルとして、お互いにリスペクトをするのであれば、相手の立場を分かってあげたり、心境を分かってあげたりしないと、相手に、
「こちらのことも分かれ」
というのは、勝手な都合でしかないだろう。
そんなことを考えていると、
人と仲良くなるということは、まずは、相手に興味を持つことが大切だ。興味もない相手と、そもそも、仲良くなろうという発想などなく、もし、これが、
「相手を利用しよう」
という考えであれば、それは、
「仲良く」
ということではなく、
「あくまでも、自分の利益優先」
ということになってしまい、そこで、お互いの立場関係を明確にしたいという意思が生まれてくるのだろう。
いわゆる、
「マウントを取る」
という考えになるのであって、最初から、お互いの力関係を考えての人間関係に、
「仲良く」
というワードがついてくるわけはない。
もちろん、次第に、お互いに共通点を持っているとすれば、その共通点がお互いに励みとなり、
「一足す一が二」
ではなく。
「三にも四にもなる」
ということを追い求める関係になるというのは、いいことではないだろうか。
それがいわゆる、
「ライバル」
というものであり、逆に、
「ライバルがいないと、士気が上がらない」
ともいえるかも知れない。
軍隊などでもそうではないか。平時には、日ごろから訓練を行っているが、その時には、必ず、仮想敵なるものがあって、その存在を撃破するべく、訓練を行っているわけである。
もちろん、実際に敵が現れて、そこが、まったく仮想敵とは違ったものである可能性もなきにしもあらずであるが、だからといって、
「すべての国を仮想敵として訓練する」
というのは、まず不可能なことで、
「どこか一つ、有事になる可能性があるか、あるいは、訓練するのに、ふさわしい国を定めて仮想敵とする」
というのが、一番ふさわしいことなのではないだろうか?
あくまでも、戦争における、
「仮想敵」
という発想だから、どうしても、そうなってしまうのであって、スポーツや、趣味のライバルであれば、まずは、自分のレベル向上に向けての努力を惜しむことなく行い、そして、初めて、ライバルである相手を意識して、相手の情報を収集し、さらに、同時に自分の力量というものをわきまえたところで、初めて、自分のレベルが相手に対して、どのあたりにいるのかということを考えることで、
「仮想敵」
というものを、まともに意識することができるのだろう。
「相手が見えていないと、とても相手になるものではない」
ということで、ライバルが見えるようになることは、自分が成長する過程での、
「通過点」
であり、
「自分を顧みることができる」
いや、
「しなければいけない」
という場所なのだろう。
「ライバルというものは、こちらの長所も短所も分かっているのだろうか?」
と考えることがある。
例えば、野球などでもそうなのだが、
「得意なコースの近くに、弱点がある」
などと言われたりする。
それじゃあ、
「相手の弱点が分かっているのだから、こちらのものだ」
というと、
「おっとどっこい、そういうわけにはいかない」
つまりは、人間の心理的なものが問題になるのであろう。
ただ、その前に、根本的に考えることがあった。
というのは、
「ライバルが一人とは限らない」
というものだった。
というのは、昔の昭和時代に流行った、
「スポーツ根性もの」
などのことであるが、よくあるのが、
「魔球のようなものを開発して、ライバルと戦う」
というものであった。
身体を駆使したり、理論的に相手がそのボールを理解しなければ、
「まず打倒することはできない」
というものがあるだろう。
そんなマンガや、テレビアニメには、まず、パターンがある。
「ライバルが数人いることや、特訓してライバルに打てないような、もっといえば、ライバルに打てないのだから、他の選手に打てるわけはないという設定」
というものがある、
そして、
「こちらが血の滲むような特訓で、魔球を編み出すと、ライバルたちは、外の選手との勝負を二の次にして、ライバルとの勝負に勝つために、必死になる」
というのだ。
主人公が開発した魔球は、ほとんどの場合、
「普通の打法では打倒が不可能」
というような球を投げてくるのだ。
その魔球を攻略しようと考えると、自ずと、それまでの打ち方がおろそかになってしまい、いわゆる、
「基本の打法」
というものから外れてくることになる。
ということは、
「普通に投げてくう選手のボールが打てなくなる」
ということである。