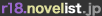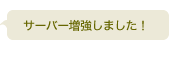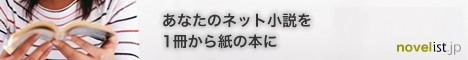機動戦士ガンダムRS 第五話 マン・マシーン解説
複雑な機体構造やその高機動・高出力・重装甲は、とても量産可能な代物ではなかったがそれゆえに総合性能は4年後のメサイア戦役時のMSをも凌駕すると言われている。
その後ガンダムマッドネスなどから収集したデータを元にして機体構造を簡略化した廉価版のガンダムサイガーとさらに高性能なガンダムエンペラーが開発された。
名称 ガンダムエルフ
形式番号 AMM-004
製造 アナハイム・エレクトロニクス社
全高 18m
本体重量 32.1t
全備重量 48.2t
出力 19830kw
推力測定不可能
装甲材質 ガンダリウムγ
武装
メガビームライフル
ビームザンバー兼メガビームキャノン×2
頭部90mmバルカン砲×2
V.S.B.R×2
G-M.B.B
メガビームシールド
フィン・ファンネル×12
その他 ミノフスキードライブ×2
機体解説
バイオ脳専用機に開発された機体である。
MMとしての基本性能や汎用性はもちろん、運用面も重視した設計が行われている。
戦闘が長期化した場合を考慮して信頼性と耐久性を重視しサイコミュ関係の一部を除いてなるべくコロニー軍の規格を採用し調達が容易な素材や部品を用いるよう心掛けられている。
部品流用が行われた背景には、ファンネルの開発が失敗した際にガンダムマッドネス二号機として運用できるように保険としてしたからだった。
ガンダムタイプで初めてファンネルを装備した機体でもある。
ミノフスキードライブに設けられたファンネル・コンテナに収納されている。
コンテナには、ファンネルのエネルギーおよびプロペラントの補給機能が備わっているため連続使用が可能となりファンネルの運用能力の向上と使用可能時間の延長に貢献している。
武装解説
フィン・ファンネル
背面の2つのファンネルコンテナに6基ずつ合計12基を格納している。
従来のファンネルとは異なり開放式バレルが採用されているためでこれは、破壊力を重視したコンセプトによる。
開放式バレルは、ビームの収束が難しく発射後にすぐに拡散してしまう。
しかし遠隔操作により敵機に急接近してから射撃するため射程距離の問題はさほどデメリットには、ならない。
従来のファンネルとは、異なるジェネレーター内蔵式のため大型化しているが活動時間が長くなりビームの出力も高い。
名称 ガンダムユベリーグン
形式番号 AMM-003
製造 アナハイム・エレクトロニクス社
全高 22.11m
本体重量 23.4t
全備重量 51.5t
出力 21460kw
推力測定不能
装甲材質 ガンダリウムγ
パイロット リード・フォックス
武装
ダブルメガビームライフル
ハイパービームザンバー兼メガビームキャノン×2
肩部90mmバルカン砲×2
V.S.B.R×2
ブランドマーカー(ビームシールド)×2
18連装2段階ミサイルランチャー×2
ハイ・メガ・キャノン
その他 ミノフスキードライブ×2
機体解説
ガンダムユベリーグンは、アナハイム・エレクトロニクス社がガンダム四天王開発計画における究極のガンダムを目指して開発した機体である。
全領域での運用能力と機動力の強化は勿論のこと一方で重装甲・大火力志向の強い機体でもありこれらの要素を同時に成立させている。
機体各部には、新開発の熱核ジェット/ロケット・ジェネレーターが複数搭載されている。
このジェネレーターは、機体の主動力源としての役割に加え熱核ジェット/ロケット・エンジンとしての共用機構を備えており大気圏内外において高性能のスラスターとして機能する。
従来のものよりも小型化されているが単基でもMM1機を十分に稼動可能である。
合体形態時には、総てのジェネレーターが直列に接続され高出力となる。
この破格の出力が複数の高機能デバイスの搭載を可能とし本機に全高20m級というサイズを越えた性能を付与している。
機体各部に分散配置されるジェネレーターの中でもバックパックに搭載されるものは特に出力が高く通常のMMのレベルを凌駕する出力を有する。
バックパック・モジュールは、本機において最も大きな内部容積を有する部位であり搭載される熱核エンジンは本来であれば航宙艦艇に積載されるクラスのもので単基でその艦艇の全電力を賄えるとされている。
MM形態時には、加速用のメインバーニアユニットとして機能し大型の航宙艦艇並みの推進力を機体にもたらす。
さらにMA形態では、腕部及び脚部のジェネレーターに直結したノズルが全て展開され推力・航続距離ともに高速巡洋艦並みの能力となる。
MA形態からMM形態へと移行する際に腕部・脚部の大口径ノズルは、機体内部に格納されMS形態時におけるスペック・ノート上の比推力は、リズィーシーガンダムよりも抑えられる形となる。
しかし実際には、余剰出力が全身に分散配置された姿勢制御スラスターへと供給されており推力を多方向に分散させているに過ぎない。
つまりMMの格闘戦には、複雑かつ応答の速い機体機動が必要となるため推力ベクトルを分散させた方が効率が良いためである。
姿勢制御スラスターは、リズィーシーガンダムの4倍に相当する32基を搭載し可変ベーンによる推力偏向が可能である。
設置数・分散率において他のガンダムと比較して突出している。
本機は、大出力エンジンと姿勢制御スラスターによって優れた空間戦闘能力を有してはいた。
しかしそれに比例して機体の操縦難度も高くパイロットへの負荷は、大きい。
変形・合体機構を有する都合上ムーバブルフレームは、構造的に複雑にならざるをえなかったが本機のそれは「MM+航空 / 航宙機+大出力火器」という複数の要素を満たすべく様々な試行錯誤が結実している。
リズィーシーガンダムのムーバブルフレームは、既存の構造と比較にならない程高い強度を備えていた。
本機は、コア・ブロックを導入した点を除けばリズィーシーガンダムとほぼ同等の変形機構を有しており複雑な変形をほぼ瞬間的に行うことが出来る。
重層的な構造を持つ可動モジュールと装甲は、マグネット・コーティングを標準で施された各部のヒンジやスライドレールによって分離しつつ堅固に結びつき、本来矛盾する機能である“柔軟さ”と“堅牢さ”を同時に実現する。
本機の四肢は、熟成されたムーバブル・フレーム技術の粋が集約された複合的なモジュールであり巨大なベクタード・ノズルとしてさらにAMBACユニットとしても十全に機能する。
マニピュレーターは、上昇しようとするMM用エレベーターを強引に牽引するトルク性能がある。
また脚部は、走行・跳躍といった人型機動兵器としての基本的な機能を備えた上で多数のスラスターを搭載し歩行/機動ユニットとして高い完成度を有している。
機体構造は、高度にユニット化が進められており改修や換装への対応に万全を期している。
各部のユニットは、複雑且つ繊細な設計であったが機体全体としては極めてシステマティックな構造を有していた。
メンテナンスの所要時間は、機体全体のオーバーホールと並行した場合でも数時間程度であったとされている。
作品名:機動戦士ガンダムRS 第五話 マン・マシーン解説 作家名:久世秀一