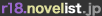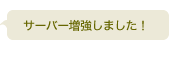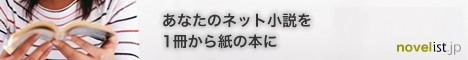倫理的で道徳的とは限らない。
オーストラリアで飼育されているミミナガバンディクート。自然の生息域の大部分において、個体数が減少している。欧米ではイースター(復活祭)に、ウサギがシンボルになる。いわゆる「イースター・バニー」だ。 だが、外来種のウサギが大繁殖して生態系が大いに乱された歴史をもつオーストラリアでは、ウサギをもてはやすかわりにミミナガバンディクート(学名:Macrotis lagotis)に注目を集めようとしている。(参考記事:「24匹が8億匹に! ウサギで豪大陸を侵略した英国人」)オーストラリアの固有種であるミミナガバンディクートは、ビルビーやフクロウサギとも呼ばれる耳の長い有袋類で、砂漠に巣穴を掘って暮らす。かつてはオーストラリア大陸の80%以上の地域に生息していた。(参考記事:「絶滅寸前の有袋類、化石の地への移住で保護へ、豪」)しかし、生息地の喪失や外来種の影響で、この数十年減少を続け、今では西オーストラリア州、クイーンズランド州、ノーザンテリトリーの一部に生息するのみとなった。国際自然保護連合(IUCN)とオーストラリア政府は、ミミナガバンディクートを危急種(vulnerable)に指定している。(参考記事:「絶滅危惧種タスマニアデビルが豪本土に復帰、3000年ぶり」)そこで「Foundation for Rabbit-Free Australia」や「Save the Bilby Fund」といった保護団体は、キリスト教の復活祭を象徴するキャラクターとして「イースター・バニー」ならぬ「イースター・ビルビー」のイメージを広めることで、ミミナガバンディクートの窮状について国民の関心を高める活動を行ってきた。2019年3月にドーソン氏が学術誌「Journal of Zoology」に発表した論文によると、ミミナガバンディクートが作るらせん状の深い巣穴は、オオトカゲや猛毒のヘビを含む、少なくとも45種の生物の避難所になっているというのだ。ドーソン氏の主張によれば、ミミナガバンディクートが減り続けると、その巣穴に避難してくる多くの種の生存が危うくなる可能性がある。2021.04.04 ミミナガバンディクートがもたらす恩恵 ミミナガバンディクートが暮らすのは、オーストラリア内陸部の荒野。気温は40℃に達することもあり、森林火災が定期的に発生する。彼らは、ほとんどの時間を深さ2メートルほどの巣穴で過ごすことで、こうした極端な環境から身を守る。 ミミナガバンディクートは、ほぼ真っ平らで何もない地形に穴を掘ることで動物たちのオアシスを作っていると、ドーソン氏は言う。ミミナガバンディクートは、体は小さいが1日に数個も巣穴を掘ることができ、巣穴を掘ることで土壌に空気を含ませ、植物がより繁殖しやすい生態系を作っていると、ウィントル氏は付け加える。「ミミナガバンディクートを救えば、重要な他の多くの種も救うことになります。オーストラリアには恐ろしい絶滅の歴史がありますが、ミミナガバンディクートを絶滅種のリストに加えさせるようなことは、私の目の黒いうちは決してさせません」と同氏は語る。
クロアシイタチは、イタチの仲間としては数少ない北米原産種のひとつ。長くほっそりとした体をもち、夜にプレーリードッグを狩って食料にしている。1日の9割を、プレーリードッグから奪った地下の巣穴で過ごす。(参考記事:「【動画】絶滅が危惧されるクロアシイタチを野生に」)
高千穂神社 創建は約1900年前。御祭神は高千穂皇神で別名、十社大明神とも。高千穂郷八十八社の総社。
絶滅危惧種タスマニアデビルが豪本土に復帰、3000年ぶり 半年で26匹が保護区の環境に適応、“野ネコよけ”など生態系への好影響に期待 2020.10.07 獰猛な性格で知られるタスマニアデビル。ここ数十年、伝染性の顔の悪性腫瘍に苦しめられている。タスマニアデビルは、絶滅の危機にさらされている有袋類だ。小型犬ほどの大きさで、獰猛な性格と強力なあごはよく知られている。あごの力は、大きな動物の死骸もあっという間にばらばらにしてしまうほど。だが、1990年代に伝染性の顔面腫瘍性疾患(DFTD)が広まったことで、タスマニア島での野生の生息数はわずか2万5000匹まで落ちこんだ。(参考記事:「絶滅危機のタスマニアデビル、「死の病」克服の兆し」)オーストラリア本土で姿を消した理由はわかっていないものの、人間が関連している可能性が高そうだ。狩猟を始めたばかりの人間が大型の動物を狩り、タスマニアデビルが食べるものがなくなったからではないかと考えられている。死体などの腐肉も食べるタスマニアデビルは、バランスのとれた健全な生態系を維持するうえで重要な役割を果たす。オーストラリア本土に再導入しようという試みが懸命に行われているのはそのためだ。「10年以上にわたる活動で、ようやくここまでたどり着きました」と、種を回復する活動を行っている団体「Aussie Ark」の代表を務めるティム・フォークナー氏は話す。この団体は、「Global Wildlife Conservation」や「WildArk」といった非営利組織とも密接に連携し、飼育した動物をオーストラリア本土のバーリントン野生生物保護区と呼ばれる場所に放す活動を行っている。この保護区は、フェンスで囲われた約4平方キロメートルの土地で、オーストラリア東部にあるバーリントン・トップス国立公園のすぐ北に位置する。「怖い動物だと言われていますが、人間や農作物にとって脅威になることはありません」と、フォークナー氏は付け加える。
コウモリやセンザンコウから別の動物(中間宿主)を経てヒトに感染した可能性が高いという結論について、「我々の多くがずっとそう考えてきました」と、米コロンビア大学感染症免疫学センター長で、2020年1月に中国で仕事をしていたイアン・リプキン氏は言う。だが氏は、「中間宿主を特定しておらず、まだ不確実です」とも付け加えた。
作品名:倫理的で道徳的とは限らない。 作家名:MultipleWoun