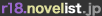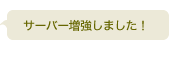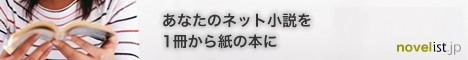倫理的で道徳的とは限らない。
中国、深センの野生動物市場で生きた爬虫類や哺乳類を売る人々。中国では54種の野生動物が食用として合法的に取引されている。新型コロナウイルス感染症の流行は生きた野生動物の取引に世界の目を向けさせた。シマアオジという絶滅危惧種も含まれていた。シマアオジが近年激減している主な理由は、一部の中国人が好んで食用にしているからだ。広州(中国南東部の1400万の人口を抱える都市で、シマアオジの主な渡り先でもある)では野生動物を食べることはごく一般的だが、北京市民が野生動物を食べることはめったにない。多くの動物が、食用、医薬品用、記念品用、ペット用に密猟され、違法に輸出入されている。この取引を強力に支えているのは、動物の体の一部に病気を癒やす力があると信じる中国の伝統医学産業だ。(参考記事:「珍しい動物のペットが中国で人気上昇、心配の声も」)中国の伝統薬に使われるセンザンコウのうろこ。需要は非常に大きく、ヒトを除いて、世界を飛び交う数が最も多い哺乳類だ。中国政府は、ミンク、ダチョウ、ハムスター、カミツキガメ、シャムワニを含む54種の野生動物について、農場で繁殖させ、食用に販売することを許可している。ジョウ氏によると、一部の繁殖業者は、自分たちの動物は保全のために飼育下で合法的に繁殖させたものだと主張しているが、市場やコレクターへの販売も認めているという。中国に生きた野生動物を取引する市場がいくつあるのかは不明だが、専門家は、数百に及ぶのではないかと見積もっている。カエルは大衆的で安価な食材です、と言うのは、ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルの中国政策の専門家で、米ヒューストン大学ダウンタウン校の東アジア政治学教授であるピーター・リー氏だ。一方、ハクビシンのスープ、コブラの揚げ物、熊の手の煮込みなどの高級料理を食べられるのは金持ちだけだと説明する。(参考記事:「ヤマアラシの密猟が横行、狙いは体内の「石」」)リー氏自身は、子どもの頃からそのような料理は食べたことはないと言う。「両親が野生動物を料理することはなく、家族で野生動物を食べたことは一度もありません。ヘビを食べたこともありませんし、ましてやコブラなんて」次ページ:同じ市内でも異なる文化
メスと過ごすセシル。黒く長い豊かなたてがみを持つ堂々たるこの百獣の王は人を恐れないことでも知られていた。2015.08.04
このところ、セシルの射殺に対し世界的に非難が高まっている。そんなライオンは知らないという人を探すのが難しいほどだ(参考記事:「なぜライオンは今も狩猟の対象なのか?」) だが、ライオンはこれまでにも趣味の狩猟(トロフィーハンティング)によって殺されてきたし、同じことが今後も続く可能性が高い。では、セシルの死はなぜこれほどまでに世界の人々を悲しませているのだろうか。ステープルカンプ氏は、セシルは自動車が近づいても気にしなかったと振り返る。約10メートルの距離まで接近を許したこともあり、「写真撮影や研究が非常にしやすかった」という。ステープルカンプ氏はある時、セシルが群れのライオン約20頭とともにゾウの死骸を食べているのを目にした。観察にはもってこいの機会で、500枚以上の写真を撮った。彼らの中に長い距離を歩き回る者がいることが分かった。川が行く手をふさぐときには、泳いで渡ることさえあったのだ。ステープルカンプ氏によれば、WildCRUが首輪を着けたライオンのうち、ある1頭はワンゲ国立公園から240キロも移動し、国境の向こうにあるザンビアの都市リビングストンに入っていたという。このライオンは、激流で知られるザンベジ川を泳いで渡ったようだ。
欧州の豪雪「東の猛獣」は海氷が減ったせいだった、最新研究 ローマに雪を降らせた2018年の豪雪、北極海海氷との関連示す画期的な手法 2021.04.06 2018年2月から3月にかけて、ヨーロッパは歴史的な大寒波と豪雪、いわゆる「東の猛獣(Beast from the East)」に見舞われた。南はローマまで雪が降り、英国では猛吹雪で高さ約8mもの雪溜まりができたほどだった。 最新の研究により、この豪雪には、ノルウェーとロシアに囲まれた北極海の一部であるバレンツ海の海氷の減少が関係していたことが明らかになった。降雪量の88%に相当する1400億トンもの雪が、その年に海氷が異常に少なかったバレンツ海から蒸発した海水に由来した可能性があるという。新たな手法による今回の研究は、北極海の海氷の減少が、はるか南の天気に影響を及ぼしうることを示している。
アイルランドが、在来種のヘビのいない珍しい国であることは本当だ。このような場所はニュージーランドやアイスランド、グリーンランド、南極大陸など、世界でも数えるほどしかない。多くの科学者が指摘するのは、今から1万年前まで続いた直近の氷河期のアイルランドは、爬虫類が暮らすには寒すぎたということ。そして氷河期が終わったときには、この島は海に囲まれ、ヘビが渡っていくことはできなくなっていたというものだ。大地を覆っていた氷が解け、マンモスが北方に遠のいていった頃、北欧と西欧にはヘビが戻り、北極圏にまで分布を広げた。 約6500年前まで陸橋で欧州本土とつながっていた英国のグレートブリテン島には、ヨーロッパクサリヘビなど3種のヘビが定着した。 しかし、アイルランド島とグレートブリテン島をつなぐ陸橋は、その2000年ほど前に氷河が解けて海になったと、モナハン氏は述べている。2021.03.17 ヒグマ、イノシシ、オオヤマネコなどの動物は、海が越えられないほどになる前にアイルランドへ到達していたが、「ヘビは違った」という。「ヘビの個体群が新しい地域に定着するには時間がかかります」とモナハン氏。
ニワトリはこういった闘いには向いているのかもしれない。首を前後させながら動くため、猛毒を持つコブラは狙いをつけにくいようだ。鳥はよくヘビを狙うもので、ニワトリも必要があれば毒ヘビを殺して食べることが知られている。飼われているニワトリも、ヒヨコや卵を狙う動物にはいつも注意している。だが、大きなヘビには負けることもあり、ヒヨコが殺されたり、卵が食べられたりすることもある。(参考記事:「雌雄モザイクのニワトリの謎を解明」)ニワトリとヘビの関係は神話にも登場する。バシリスクという、ヘビの姿をした伝説上の生き物は、雄鶏の鳴き声が弱点だとする話がある。
作品名:倫理的で道徳的とは限らない。 作家名:MultipleWoun